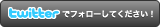自家製甘夏ピール
2009.05.09 |Category …手作りお菓子
生協で無農薬有機栽培の甘夏の注文がありました。
そして、チラシには甘夏ピールの作り方ものっていました。
これはおもしろそう!さっそく注文しました。
1ネット3個分で、皮の重さは300gくらいでした。
皮は3~4回茹でた後、一晩水にさらすと苦味がとれて柔らかくなるそうです。
やっぱりコツは、ひと手間かけることなんですね。
水をきった皮を80%くらいの粗糖で煮るだけです。
ピールとしてそのまま食べるなら、5~7日完全に乾燥させてお好みでグラニュー糖をまぶして保存します。
母はパンやお菓子にそのまま使うつもりで、しっとりした状態のままガラス容器に保存しました。
これでどんなおいしいパンが焼けるかな?楽しみです。
そして、チラシには甘夏ピールの作り方ものっていました。
これはおもしろそう!さっそく注文しました。
1ネット3個分で、皮の重さは300gくらいでした。
皮は3~4回茹でた後、一晩水にさらすと苦味がとれて柔らかくなるそうです。
やっぱりコツは、ひと手間かけることなんですね。
水をきった皮を80%くらいの粗糖で煮るだけです。
ピールとしてそのまま食べるなら、5~7日完全に乾燥させてお好みでグラニュー糖をまぶして保存します。
母はパンやお菓子にそのまま使うつもりで、しっとりした状態のままガラス容器に保存しました。
これでどんなおいしいパンが焼けるかな?楽しみです。
PR
よもぎ復活
2009.05.06 |Category …手作りお菓子
ゴールデンウィーク最後の日。
やってみたいと思っていて忙しくてできなかったこと第3弾。よもぎ餅作りに挑戦です。
4月のとある日曜日、たまへいがお友達と近くの池に釣りにでかけました。
お友達が山菜にとても詳しくて、これはよもぎ、これはぜんまいと教えてくれたそうです。
彼のおじいちゃんは山の人。釣りや山菜採り、昆虫採集が趣味なんだそうです。
たまへいは、よもぎを根っこをつけたままお持ち帰りしました。
庭の片隅に植えておいたら、翌日にはクタンと萎れてしまいました。
もうだめかなと思っていたら、2~3日後には元気になったんです。
よもぎ復活!植物の生命力に感動です。
たまへいの気持ちを大切にしてあげたくて、「このよもぎでよもぎ餅を作ろうね。」と約束しました。
 いつもパン生地をこねる時活躍する「こねまるくん」
いつもパン生地をこねる時活躍する「こねまるくん」
餅つきもできるんです。
本には、前の晩にもち米を水につけておいて
蒸し器で蒸すと書いてありました。
炊飯機でもうまくいくかなと思い、
炊飯機で炊いたもち米を「こねまるくん」に入れたら
べとべとのお餅になってしまいました。
よもぎは葉先をつんで塩茹でして細かくきざんで準備
完了です。
べとべと餅によもぎを混ぜたら、うまく混ざらず
まだらのよもぎ餅になってしまいました。
アボリーゼのお友達も一緒に
みんなでやわらかいお餅をスプーンですくって
おいしいおいしいと食べました。
とってもやわらかくて、お餅じゃないような食感。
ちょっと失敗でしたが、子供達が喜んでくれたのでなによりです。
よもぎは茹でた後ミキサーにかけたほうがいいかな?もち米の水加減は?
つきたて餅の上手なとりわけ方は?
もちつき機のコツ、今度はうまくいくように勉強しておきますね。
やってみたいと思っていて忙しくてできなかったこと第3弾。よもぎ餅作りに挑戦です。
4月のとある日曜日、たまへいがお友達と近くの池に釣りにでかけました。
お友達が山菜にとても詳しくて、これはよもぎ、これはぜんまいと教えてくれたそうです。
彼のおじいちゃんは山の人。釣りや山菜採り、昆虫採集が趣味なんだそうです。
たまへいは、よもぎを根っこをつけたままお持ち帰りしました。
庭の片隅に植えておいたら、翌日にはクタンと萎れてしまいました。
もうだめかなと思っていたら、2~3日後には元気になったんです。
よもぎ復活!植物の生命力に感動です。
たまへいの気持ちを大切にしてあげたくて、「このよもぎでよもぎ餅を作ろうね。」と約束しました。
餅つきもできるんです。
本には、前の晩にもち米を水につけておいて
蒸し器で蒸すと書いてありました。
炊飯機でもうまくいくかなと思い、
炊飯機で炊いたもち米を「こねまるくん」に入れたら
べとべとのお餅になってしまいました。
よもぎは葉先をつんで塩茹でして細かくきざんで準備
完了です。
べとべと餅によもぎを混ぜたら、うまく混ざらず
まだらのよもぎ餅になってしまいました。
アボリーゼのお友達も一緒に
みんなでやわらかいお餅をスプーンですくって
おいしいおいしいと食べました。
とってもやわらかくて、お餅じゃないような食感。
ちょっと失敗でしたが、子供達が喜んでくれたのでなによりです。
よもぎは茹でた後ミキサーにかけたほうがいいかな?もち米の水加減は?
つきたて餅の上手なとりわけ方は?
もちつき機のコツ、今度はうまくいくように勉強しておきますね。
はじめての日帰りバスツアー
2009.05.05 |Category …旅行
今日は、日帰りバスツアーにはじめて参加しました。
「室生寺のしゃくなげと長谷寺のぼたん」 奈良の古寺をめぐるツアーです。
実家の一族と一緒に8人で、たまおやじとアボリーゼはお留守番でした。
 室生寺は、奥深い山の中にあります。
室生寺は、奥深い山の中にあります。
朱塗りの太鼓橋を渡るとお寺の入口です。
本堂の後ろの石段を登ると美しい檜皮葺(ひはだぶき)の
五重塔があります。
平安時代初頭の建立と云われます。
五重塔から奥へ、杉の大木が鬱蒼と立ち並ぶ石段を登って
行くと奥の院へと続きます。
自由散策時間は1時間、行けるところまで行ってみようと
登り始めた石段は、登り始めたら最後、あとには引き返せなく
なってしまいました。
急な石段が延々と続き、途中で何度も息切れしながらやっとの
思いで頂上の奥の院にたどりつきました。
バスの集合時間はギリギリでしたが、頑張って登った甲斐ありました。

道の駅で昼食をとった後は、長谷寺へと向かいます。
本堂へと続く木造の屋根付き登廊です。
千社札がたくさん貼られた天井や柱を眺めながら
石段を登っていくのはとても風情がありました。
丁度、ご本尊の観音様の特別御開帳で、
観音様の御足(おみあし)に触れることができました。
木像に金箔を施された観音様ですが、
御足は400年もの間、多くの人の手によって
磨かれて飴色に輝いていました。
磨かれることによって足の部分は金箔もはがれおちたそうです。
木像も毎日手で磨くとあんなに美しくなることを知り感動しました。
美しくなるには長い年月、多くの人の手がかかるのですね。
 本堂には清水寺のような舞台があります。
本堂には清水寺のような舞台があります。
大和では、「初瀬の舞台から飛び降りる」と言うそうです。
舞台からは、雨に濡れた新緑のみどりが鮮やか。
奈良の山並みは、こんもりとしてとてもおだやかです。
バスの車窓からは、雨に濡れた緑の山々にところどころ
かすみがたって絵に描いたような景色を眺めました。
家の近くで見慣れた険しい山の景色とは随分違います。
今回の旅行で一番びっくりしたのは、おじいちゃんも
おばあちゃんも室生寺のあの急な石段を最後まで登った
こと。年をとってもあの元気さと好奇心旺盛なところ、
自分の親ながら感心しました。
地元発着のバスツアーで料金は拝観料も昼食代も含めて5,980円なり。
自分で企画する旅も楽しいのですが、こんな安価では行けませんよね。
ゴールデンウィークで大渋滞が予想されていた高速道路も、渋滞している区間は下道を走り、
トイレ休憩の時間もうまくずらして調整し予定通りの帰着でした。さすがプロです。感心しました。
バスの中ではおしゃべりしながら、疲れたらお昼寝もできて。すべてお膳立てしてもらえるのでらくちんです。
日帰りバスツアーってとっても魅力的です。
「室生寺のしゃくなげと長谷寺のぼたん」 奈良の古寺をめぐるツアーです。
実家の一族と一緒に8人で、たまおやじとアボリーゼはお留守番でした。
朱塗りの太鼓橋を渡るとお寺の入口です。
本堂の後ろの石段を登ると美しい檜皮葺(ひはだぶき)の
五重塔があります。
平安時代初頭の建立と云われます。
五重塔から奥へ、杉の大木が鬱蒼と立ち並ぶ石段を登って
行くと奥の院へと続きます。
自由散策時間は1時間、行けるところまで行ってみようと
登り始めた石段は、登り始めたら最後、あとには引き返せなく
なってしまいました。
急な石段が延々と続き、途中で何度も息切れしながらやっとの
思いで頂上の奥の院にたどりつきました。
バスの集合時間はギリギリでしたが、頑張って登った甲斐ありました。
道の駅で昼食をとった後は、長谷寺へと向かいます。
本堂へと続く木造の屋根付き登廊です。
千社札がたくさん貼られた天井や柱を眺めながら
石段を登っていくのはとても風情がありました。
丁度、ご本尊の観音様の特別御開帳で、
観音様の御足(おみあし)に触れることができました。
木像に金箔を施された観音様ですが、
御足は400年もの間、多くの人の手によって
磨かれて飴色に輝いていました。
磨かれることによって足の部分は金箔もはがれおちたそうです。
木像も毎日手で磨くとあんなに美しくなることを知り感動しました。
美しくなるには長い年月、多くの人の手がかかるのですね。
大和では、「初瀬の舞台から飛び降りる」と言うそうです。
舞台からは、雨に濡れた新緑のみどりが鮮やか。
奈良の山並みは、こんもりとしてとてもおだやかです。
バスの車窓からは、雨に濡れた緑の山々にところどころ
かすみがたって絵に描いたような景色を眺めました。
家の近くで見慣れた険しい山の景色とは随分違います。
今回の旅行で一番びっくりしたのは、おじいちゃんも
おばあちゃんも室生寺のあの急な石段を最後まで登った
こと。年をとってもあの元気さと好奇心旺盛なところ、
自分の親ながら感心しました。
地元発着のバスツアーで料金は拝観料も昼食代も含めて5,980円なり。
自分で企画する旅も楽しいのですが、こんな安価では行けませんよね。
ゴールデンウィークで大渋滞が予想されていた高速道路も、渋滞している区間は下道を走り、
トイレ休憩の時間もうまくずらして調整し予定通りの帰着でした。さすがプロです。感心しました。
バスの中ではおしゃべりしながら、疲れたらお昼寝もできて。すべてお膳立てしてもらえるのでらくちんです。
日帰りバスツアーってとっても魅力的です。